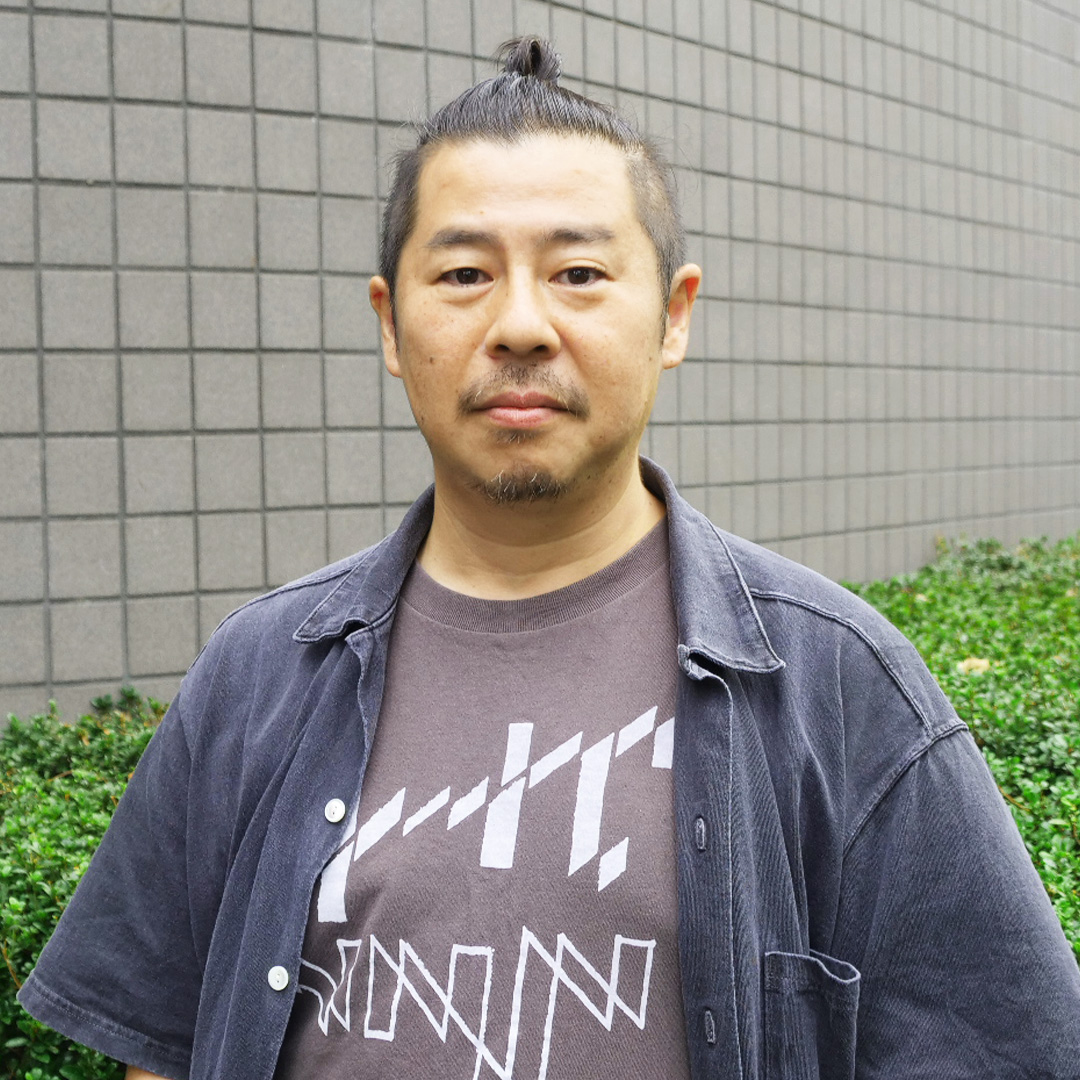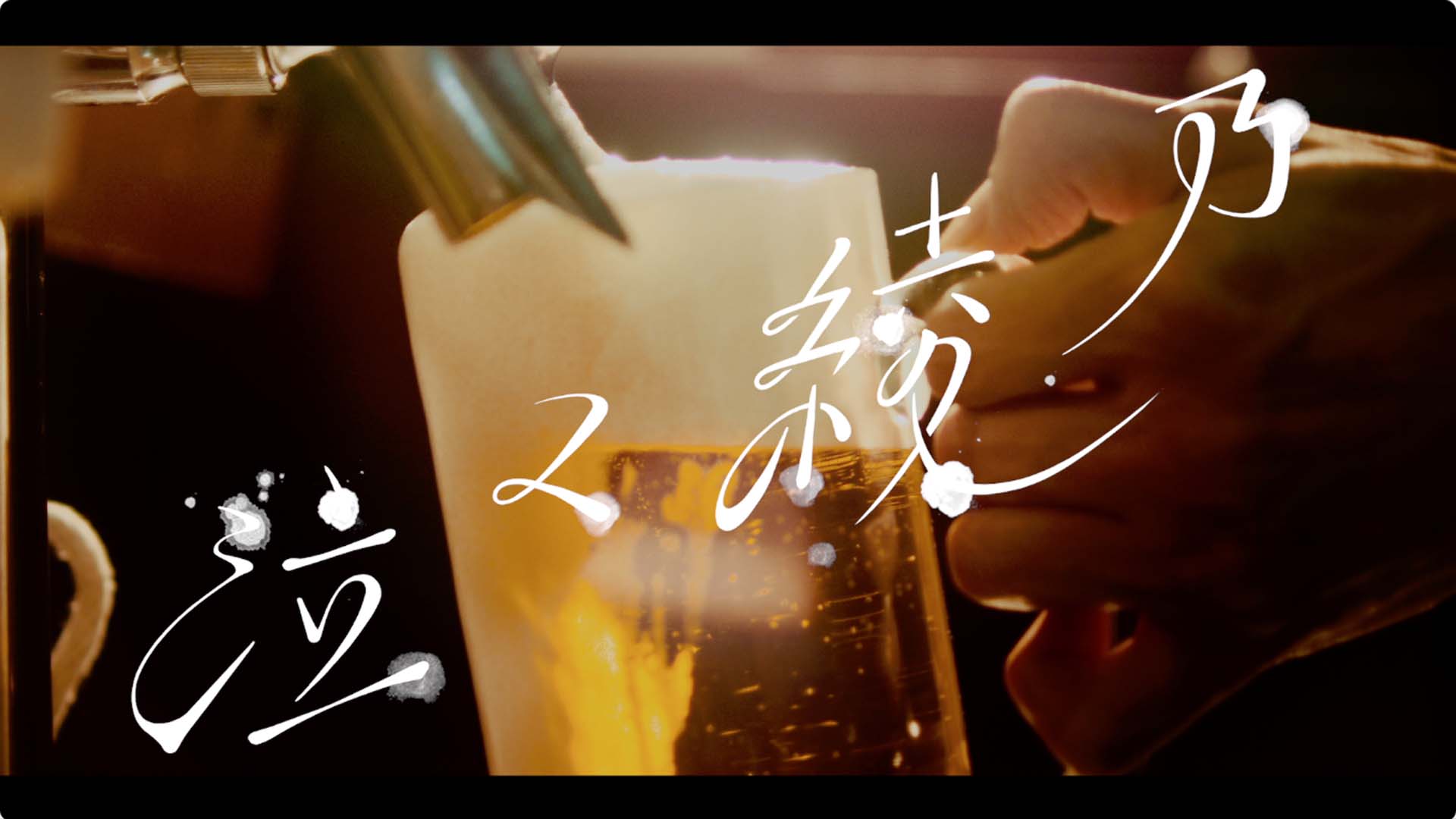短編映画監督作品の『おべんとう』について
── 板橋監督はジーンシアターで『おべんとう』、『泣く綾乃』を配信されています。まずは『おべんとう』についてお伺いします。この作品に出てくるお弁当がとても美味しそうでした。お弁当をテーマにされた理由とお弁当を美味しそうにみせるこだわりについて教えてください。
お弁当というのは、例えば遠足の時のお母さんの手作りのおにぎり一個であったとしても、記憶に残りますよね。日本人にとってお弁当に対する思いは特別であり、そのお弁当の魅力を伝えたいという思いからこの作品をつくりました。お弁当の魅力を伝えるために、美味しいことはもちろんですが、美しく見せることにもこだわりました。そのためにこの映画のお弁当は、テーブルスタイリストの西崎弥沙さんと、料理人の柳澤由梨さんにお願いしました。西崎さんは雑誌や広告などで食器やテーブル周りのセッティングなどを専門にされている方です。柳澤さんは東京で日本料理店を経営されている方で、西崎さんから紹介していただきました。お米の炊き方にとてもこだわっていて、柳澤さんの炊くご飯は本当に美味しいです。

よくCMなどで使われるテカリを塗るなどの美味しそうにみせる技はあえて使わずに、ちゃんと食べられて、美味しいものをお弁当に詰めていくことにこだわりました。いつも撮影後はみんなでそのお弁当を美味しく頂きました(笑)。この作品を見るとお弁当をつくってみたくなるようで、フランスのクレルモン-フェラン国際短編映画祭で上映されたときには、映画を観たフランス人から「あなたの映画を観て卵焼きをつくって食べてみた。美味しかった」というメールをもらいました。
短編映画紹介

『おべんとう』(ジーンシアターで配信)視聴はこちらから
ストーリー
「僕は、お弁当が好きだ」幼い頃から両親の作る弁当で育ち、大人になった今も弁当をこよなく愛する主人公は、毎日自分のために朝から弁当を詰める。
ある日会社で突然言い渡された、新しいプロジェクトへの参加。思わぬところで青年の“お弁当好き”が功を奏して、仕事はとんとん拍子にうまく進んでいき……。前任者の女性と居酒屋で祝杯をあげた翌朝―― 彼は人生で初めて、誰かのためにお弁当を作る。
── あのクレルモン-フェラン国際短編映画祭で上映されたのですね。映画祭でのノミネートはやはり感激しましたか?
実は『おべんとう』は、最初の年はクレルモン-フェラン国際短編映画祭では落選しているのです。翌年にその映画祭でフードの作品を上映する部門があって、招待作品として上映したいとディレクターから声がかかり、上映されることになりました。
『おべんとう』が初めて映画祭にノミネートされたのはモントリオール世界映画祭です。いきなり初作品が選ばれたことはとても嬉しかったし、元気をもらうことができました。ただし、裏話がありまして、その映画祭が経営破綻してしまい、その年が最後の映画祭になってしまいました。映画祭も縮小されて、『おべんとう』はノミネートされたのですが、上映されないことになってしまったので、モントリオールには行くことができませんでした。

── 初作品でもある『おべんとう』を撮るうえで苦労されたことは何でしょうか。
苦労というよりは、作品をつくっている時間はとにかくずっと楽しかったですね。そもそも『おべんとう』をつくるきっかけは、私が40歳になる前に一本映画をつくりたいと思ったことなのですが、プロデューサーにその話をしたら、当時一緒に仕事をしていたスタッフたちがすぐにたくさん集まって協力してくれました。本当にスタッフたちには頭が上がらないくらい感謝しています。
短編映画監督作品の『泣く綾乃』について
── 『泣く綾乃』についてお伺いします。この作品は実話が基になっているそうですね。
この映画は主演の工藤綾乃さんのエピソードが基になっています。工藤綾乃さんは主演映画の本番で泣くことが出来なくて、悔しい思いをして、毎日泣く練習をした写真を一年間マネージャーに送ったそうです。その写真を見たプロデューサー、監督、役者仲間が工藤さんに励ましのメッセージボードを送るようになり、あるとき私にも書いてくださいという依頼がきました。私はその写真を全部並べて、動画にして工藤さんにプレゼントしましょうと提案したのですが、だったらそれを映画にできないかという話になったのがきっかけです。
短編映画紹介
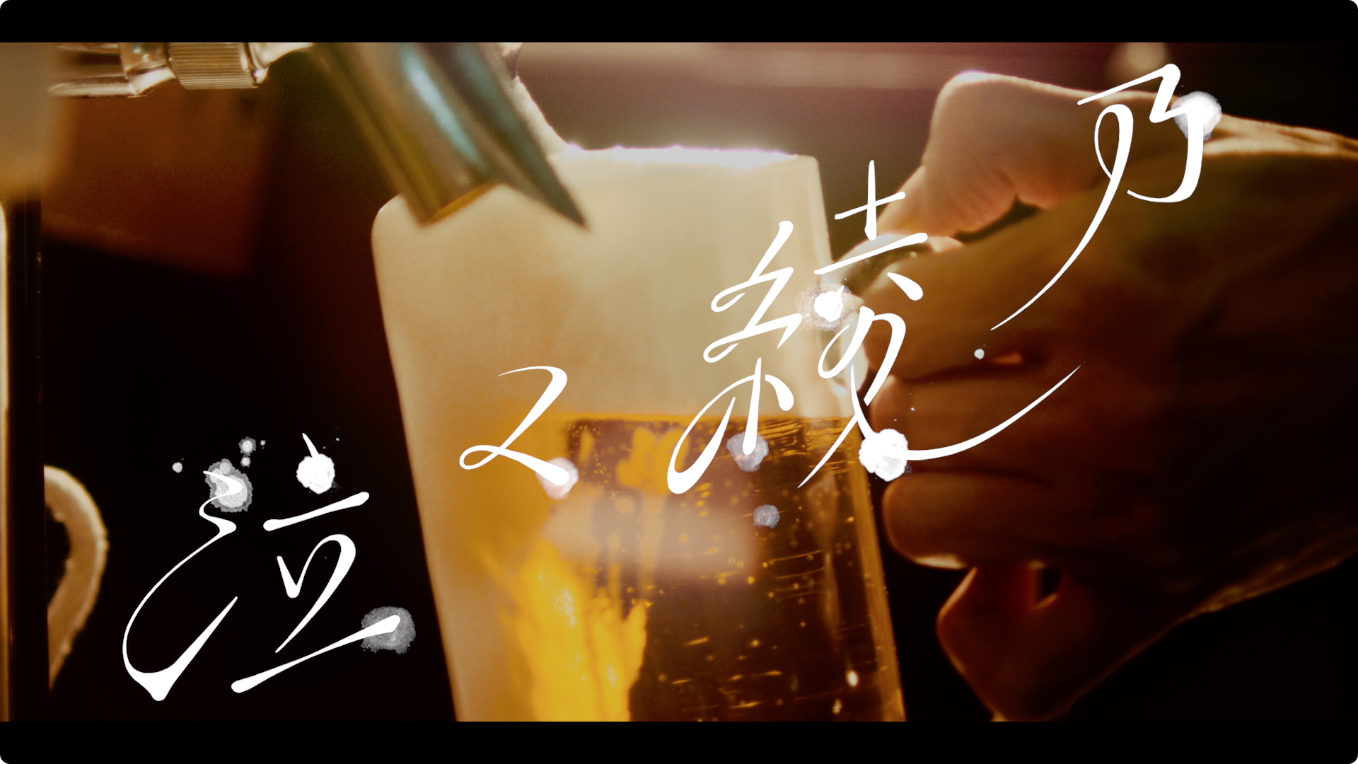
『泣く綾乃』(ジーンシアターで配信)視聴はこちらから
ストーリー
劇団に所属する女優・綾乃は、次の新作舞台での主演に大抜てきされる。
今作のテーマは「涙」――過去最大キャパシティとなることもあり、売れっ子俳優も出演することが決定。日夜、稽古場には団員らの熱い想いが充満する。しかし、日に日に本番が近づく中、未だに綾乃は“泣く演技”ができないでいた。
焦り、葛藤、そして逃げ出したい気持ちに苛まれる日々を経て、いよいよ舞台は本番の時を迎える……。
── 主役の工藤綾乃さん以外の登場人物にも存在感があると感じたのですが、人物設定や背景は考えましたか。
工藤さんが舞台で泣けない、泣く練習をするだけの話では面白くないと思ったので、劇団という背景を用意して、他の登場人物たちに個性や面白さを持たせようと人物設定を工夫しました。俳優さんには本人役を演じるというように、なるべく素で演じてもらうようにお願いしました。
劇団をこの映画の舞台にしたのは、学生時代にプロの劇団の演出のアルバイトを3年経験していたからです。そこで多くの俳優さんや監督さんと繋がりができて、私の書いたシナリオを読んでもらい、意見をいただいたりできたことは、私の財産になりました。舞台の世界になじみがあったことが背景を劇団にした理由です。
人と人との繋がりから、共演に俳優の落合モトキさん、奥山佳恵さんにも出演していただき、お二人の演技が作品に深みを持たせてくれました。

── バッティングセンターのシーンが印象に残りました。撮影や演出でこだわったところはありますか。
あのシーンは、ずっと引きの画面で、ボールを飛ばしたままの撮影だったので、俳優さんにはボールに当たらないように気をつけていただきました。落合さんのセリフにより、綾乃の心に変化が芽生える大切なシーンだったので、あえて真面目になりすぎないように、ボールを飛ばしたまま、周りを騒がしくする演出にしました。画面をアップにせずに、引きの画面の中でボールがバーンと転がってくる感じに虚無感があって、良いシーンになったと思います。
また、落合さんが言う「綾乃の所属する劇団の演出家が辞める」という話は、本当にも噓にも、作品を見た人がどちらにもとれるようにしたいと思いました。
──撮影で大変だったことはありますか。
予算がクラウドファンディングだったにもかかわらず、良い俳優さんたちに集まっていただいたので、予算内できちんとした体制を組まなければいけなかったこと、撮影期間が3日間しかとれなかったことで、当初のシナリオよりロケ地を減らしたり、俳優さんたちの衣装も多くを持ち寄りにしてもらったりしました。ただ本番の舞台のシーンの殺陣は、舞台人として、本物を見せることにこだわりました。殺陣師の方に入ってもらい、しっかりと稽古をして撮影に臨みました。
あとは、イメージに合った撮影場所を探すために、綾乃の部屋と居酒屋はたくさん見に行きました。
──演出についてお伺いします。撮影に入る前に脚本をつくりこんで、現場に臨む方と、あまり脚本を固めないで、現場で考えながらつくっていく方といらっしゃると思いますが、板橋監督はどちらでしょうか。演技指導や、演出のこだわりがありましたら教えてください。
しっかり脚本をつくりこんで撮影に臨むタイプです。現場で考えて作品がステップアップしたという経験がまだないからです。シナリオが9割5分くらい完成してないと撮影には臨みたくないタイプの人間ですね。
俳優さんの演技指導は、読み合わせのときに役柄の生い立ちなど方向性を伝えて、さらに現場でも、例えば下を向いたり、目をそらすタイミングや、ちょっとした癖を持たせたり、細かく指示するタイプです。
演出に関しては、特にこだわりはないというより、型がまだ見つかっていなくて、そこを模索している最中です。そのため犬童一心監督、成島出監督のワークショップに参加させていただいて、お手伝いをしながら演出の勉強をさせていただいています。
映像制作のキャリアについて
── 映像制作のキャリアは長いですが、映画の監督は39歳になってからですね。大学卒業後はどのように映像制作を学んでいったのでしょうか。
大学を卒業して、CMの制作会社で2年間映像制作を勉強しました。その後演出の道に進もうと思い、2年間フリーランスをしながら、ドキュメンタリーを制作している会社で働きました。そこでTBSのドキュメンタリー番組『いのちの響き』を5年にわたって制作し、インタビューの仕方や編集の仕方など全部その番組で学ぶことができ、今の私の礎になっています。その後は、フリーランスとして、CMやドキュメンタリー番組を制作してきました。

── 映画をつくりたいと思われたきっかけを教えてください。
大学を卒業したら映像の仕事をしたいと思っていましたが、そのきっかけをつくってくれたのは、高校2年生の時に観た大林宣彦監督の『転校生』です。映画の冒頭のシーンで、主人公が階段から落ちて、立ち上がって、その前を電車が通り過ぎる。その瞬間に画面がモノクロからカラーに変わるのですが、その映像を見たときに「映画を撮りたい」と思いました。
進学した大学では映像を学べなかったので新藤兼人監督のシナリオ講座にダブルスクールで通いました。当時劇団でアルバイトしていたので、書いたシナリオを監督に見てもらって意見を聞いたり、映画を見て良いシナリオ、言葉だなと思ったらメモを取ったり。映画のつくり方は知らないけれど、先行してシナリオの勉強をしました。
CM制作会社に入ってからはとても忙しい職場でしたが、映像をつくる現場で学ぶことができました。
40歳手前になって、やはり映画をつくりたいなと思い、『おべんとう』をつくりました。念願の映画がつくれて本当に嬉しかったです。最終日はスタッフのみんなと別れたあと、一人で泣いてしまいました。
── 映画づくりの楽しさはどんなものでしょうか?
映画づくりの楽しさは、私がまだ商業映画をあまりやっていないこともありますが、私のOKが100%OKになるというわがままな世界に行けるということでしょうね(笑)。
── 板橋監督が好きな監督や参考にしている監督はいらっしゃいますか。
市川準監督です。市川監督の作品の時間の流れや、時の空気が好きです。『つぐみ』や『東京マリーゴールド』は50回以上観ています。『BU・SU』、『東京兄弟』も大好きです。作り手として、あの空気感を出せたらいいなと思いますが、なかなか出せないですね。あとは磯村一路監督の田中麗奈さん主演の『がんばっていきまっしょい』も好きです。
東日本大震災後の神社再建への強い想いを描いた長編ドキュメンタリー
── 長編映画『そこにあるべきものたち』をつくられたのですね。
この映画は2024年の7月に完成したばかりで、まだ上映されていません(2024年11月現在)。撮影も編集も1人でやって、費用も自分で出しました。
── え、自主で作られたのですか。その理由を教えてください。
2011年の東日本大震災の年にドキュメンタリー番組をこの土地で撮っていて、その年の3月20日に放送される予定だったのですが、震災が起きて、番組は中止になりました。震災前の街並み、震災後の風景などを全部撮っていて、たまたまこの映画の舞台になった神社も取材していたのです。
震災で社殿が流されてしまい、土台だけ残っていたのですが、13年ぶりに新しい社殿が建てられました。
その土地は防災のために、松林になり、人が住めないことが決められてしまった場所です。人が住めないのに、住民の方々が強い意志で神社を建てたのです。
この住民たちの強い想いを知ってほしいと思い、映画をつくりました。

『そこにあるべきものたち』
苕野神社再建への想いを綴る長編ドキュメンタリー
福島第一原子力発電所からおよそ7kmに位置する福島県浪江町請戸。
東日本大震災の津波で壊滅的な被害を受け、原発事故の影響で住民が県内外に避難し人口が一時ゼロになりました。請戸は今、災害危険区域に制定されて、誰も住めない土地になっています。そんな誰も住めない土地に神社が再建されることになったのです。
1300年以上の歴史を誇る苕野神社。そこには、代々受け継がれてきたものたちが存在し、住めなくなった今も、無くしてはならないと繋がり活動する人たちが集います。
この映画では、再建に関わる元請戸住民と、請戸に伝わる伝統芸能を継承する方々を取材しました。流出した神社社殿の再建を決め、心の拠り所を取り戻そうとする元住民たちの精神的復興を描く、請戸への想い、苕野神社再建への想いを綴る長編ドキュメンタリー映画です。
── 人が住めないところに神社を建てたのですか!地元の方の強い想いが伝わります。
そうですね。やはり、震災前の姿を撮影した自分が映画化しなければ、という使命を感じてつくりました。
今は試写上映という形で、地元3か所で、住民の方々に観ていただくことになっています。今後は映画館で上映したいと思っています。

── 自主映画は収益に繋がらないこともありますが、つくり続けていく理由やモチベーションはどのようなものでしょうか。
映画をつくるのが楽しくて仕方がないので、お金さえあれば、ずっとつくり続けていきたいです。モチベーションになるのは、やはり世界の映画祭へのノミネートです。
出品する先としては、8割は海外の映画祭に出品しています。今後は一年に一本映画をつくり、そして映画祭に出していきたいです。
この映画監督の作品
井村哲郎
以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。
自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。