GeneTheaterアンバサダーの俳優・下京慶子さんに、キャリア、映画づくりについてインタビュー。映画づくりへの意欲、決意の言葉があふれ出ました。
初めての撮影はプレッシャーで発熱
――GeneTheaterアンバサダーを務めていただいてありがとうございます。下京さんは俳優、映画プロデューサー、ドローンパイロットと多方面で活躍されていますが、まず俳優業について伺います。映画出演で思い出に残っている出来事はありますか?
スクリーンデビューは、2020年の『ステップ』(監督:飯塚健・主演:山田孝之)という作品で、オーディションを経て、山田さんの同僚役を演じたんです。当時、映像経験はほぼなくて。それでプレッシャーを感じたのか、撮影初日に38度の熱が出たんですよ。風邪をひいたわけではなく、気持ちの面から体に異変が起きるのは初めての経験でした。それを隠して現場に行ったわけですが、「クレーンが自分の視界に入ったタイミングでセリフをください」と指示されて、フラフラした頭の中で“クレーンって何…?”となり(笑)、右も左も分からない中で、2回くらいミステイクしてしまって。苦い思い出ですが、それでも完成した作品を観たときは、作品の一員になれたことがすごく嬉しかったです。

――他にも、印象的な出来事はありますか?
2023年の『唄う六人の女』(監督:石橋義正・主演:竹野内豊×山田孝之)ですね。このときもオーディションを経て出演が決まったのですが、その後プロデューサーとドローンパイロットも兼任することになり、1カ月ほど地方現場に缶詰で、時間と労力をかけて作品を創る充実感がありました。大自然がテーマの作品で、本来撮影禁止の原生林で特別に許可をいただいて。リアルな自然に身を任せながら各部署の皆さんと石橋監督の世界を創り上げていく経験は、改めて映画ってすごいなぁ、人間ってすごいものをつくっているなぁ、と心が震えました。
――水を吐き出すシーンはCGですか?
あれは実際にやっているんですよ。「水をドバーッと吐き出す」ような画コンテだったんですが、そのままやるとあまりきれいな画にならない気がしたので、監督に相談したんです。「下京さんの自由にやってもらって大丈夫ですよ」とのことだったので、そこから試行錯誤の日々が始まりました。お風呂で毎日、いろいろなバリエーションを試して、プロレスラーの方が霧吹きみたいに吹くじゃないですか、あれもできるようになって、現場でどんな水の吐き方を指示されても大丈夫!になりました。そういえばロケバスで竹野内豊さんが「水吐くのはどうやろうと考えてるの」と聞いてくださって、「自分はこうしようと思っているんです」と言ったら、「何が良いだろうね」と一緒に考えてくださいました。一緒に作品を作っている感覚で、嬉しかったです。その後、竹野内さんのアイディアも取り入れさせていただいた結果、ほぼほぼ一発録りで現場は終えられました。ハイスピードで撮っているので、スローモーションですけど。
――スローモーションなんですね。
なるべく長く吐き出せるように口いっぱいに水を含んで、細く出して、でも重力でらせん状になるように角度も工夫してとか。一発目でOKが出て、念の為さらに2パターンぐらい撮りましたが、おそらく最初のバージョンが使われたと思います。井村さん、このシーンに注目してくださるとは(笑)
――インディーズ映画にも出演されていますが、どのようなきっかけで出演されたのでしょうか。
映画に参加したいなと思っても、オーディション案件にすら辿り着けなくて困っていたときに、知り合いの俳優さんに“シネマプランナーズというサイトがあるよ”と教えてもらったんです。そこでキャストやスタッフが募集されていて、応募してみたら出演が決まりまして。『あいている鳥カゴ』 (監督:安藤チカラ)『ドブ殺しは愛のきらめき』(監督:合田雄太)『ディスコーズハイ』(監督:岡本崇)などに出演しました。
――ご自分で応募して、オーディションで決まったのですね。他の出演映画『とどのつまり』(監督:片山享)は主演でしたが、主演ではない映画とは心構えなどに違いはありましたか?
心構えに違いはないですね。あの頃は主演でも主演じゃなくても、自分の役割を全うしようと思って参加していたので。でも主演のほうが撮影シーンが多くて日々積み上げていけるものがあるせいか、いつもより自然体でいられる感覚がありました。トリプル主演だったのもあるかもですね。私1人だけじゃなかったので、それもあるかもしれないです。
<『とどのつまり』予告>
https://www.youtube.com/watch?v=rkYOkp2_e6w
商業映画、自主映画、それぞれの良さ
――下京さんは商業映画もインディーズ映画にも両方出演されているのでぜひ伺いたいのですが、それぞれの良さはどういうところにありますか?
商業映画は予算が大きいので、時間も人も多く確保できる分、やれることが増える。準備期間も長くとれるし美術もロケ地もこだわることができるので、商業でしかできない表現があると思います。大きいセットにCGまで足して世界観をつくり込んでいけるのが、商業の良さですよね。
インディーズ映画は、基本的に自分たちで出資してつくりたいものをつくるから、現場での柔軟性・自由度が高い。例えば現場で監督が「こういう美術も欲しいんだけど」と言い出したら、近くのホームセンターで買ってきたものを接着してペンキを塗ってつくる、といったようにその場で工夫できるのが面白いです。予算が限られていて人数も多くないので、撮影は大変なことも多いですが、「やってやろうぜ」みたいな空気感、火事場の馬鹿力のようなエネルギーが生まれやすい点もあり、それが作品にとって良い効果をもたらすこともあるなと感じています。
――日本アカデミー賞で2回受賞している藤井道人監督のドラマ(テレビ東京系列『日本ボロ宿紀行』)に出演されたことがありますね。藤井監督の演出はどのような感じでしたか。
とても丁寧に演出される方です。私はその現場がドラマ初出演で、俳優としても日が浅いほうでしたが、そんな私にも敬語でコミュニケーションも細部まで取ってくださって、経歴や番手に限らず平等に接してくださる方という印象でした。すごく素敵な監督さんだと感じましたし、現場のキャストの皆さんも藤井監督を信頼しているように思いました。有名になられた今も、当時と変わらず丁寧にキャストの皆さんに接されていて、キャストの力を信じてくださっている監督とお互いの信頼関係が積み重なって、熱の高いシーンがつくられていくように感じます。
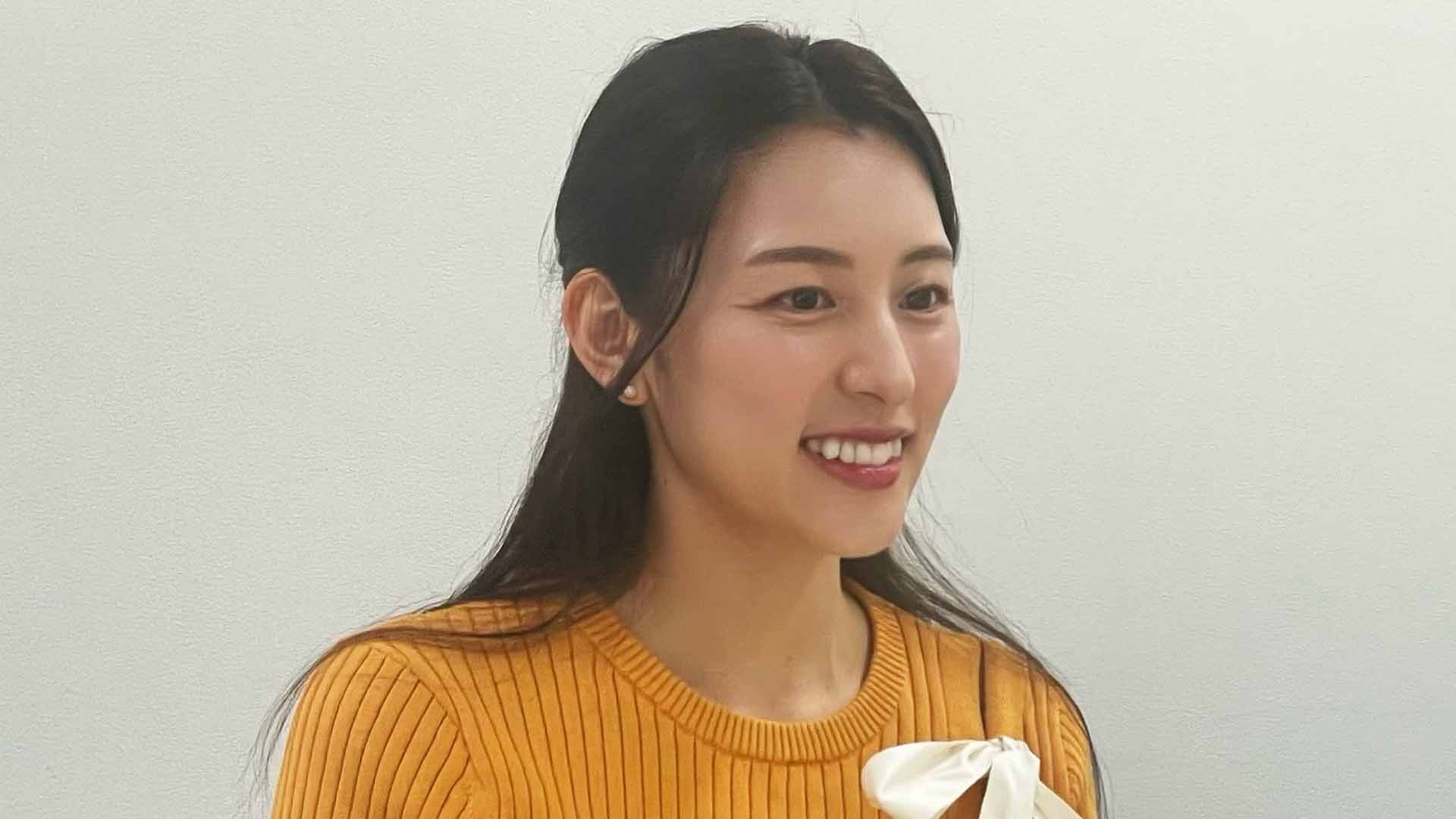
――最近は縦型ショートドラマにも出演されていますが、映画やテレビドラマとは取り組み方が違うのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。
縦型ショートは、より瞬発力が必要です。通常のドラマよりも短い撮影期間と尺の中で、表情にしろ感情にしろ、立ち振る舞いにしろ、特に感情かな?一瞬でその場の状況を視聴者に提示してあげないといけないのが、私のような不器用な役者にとってはすごく難しいと感じています。
――切り替えが大変なんですね。今泣いたらすぐ次は笑って、とか。
おっしゃる通りです。『マリッジプラン』という縦型ショートドラマをプロデュースしたこともあるのですが、毎話3分の中に常に山場のシーンがあるような構成だったので、展開がスピーディーな中で感情もいったりきたりで大変だったと、キャストの皆さんが話していました。その後、実際に私もキャストとしてショートドラマに参加してみて、皆さんが言っていた意味を大変に理解しました。(苦笑)。泣いたり、怒ったり、トラブルに巻き込まれたりと常に山場を演じている状態で、体力も必要になりますね。
――役者さんは2タイプあると思うのですが、撮影期間中は私生活も役に入ったままのタイプか、私生活では切り替えて現場で役に入るタイプか。下京さんはどちらのタイプですか。
どちらかというと、私生活も役に入ったままのタイプです。今は制作もやっているから、その時が切り替えの時間になっています。でも本当にやってみたいのは、朝起きて夜寝るまで、その役のことしか考えなくていい環境に身を置くこと。あまり声を大にしては言えませんが、現状はそれができていないので、今後は制作のスケジュールをうまく組んで、それが出来るようにしようと思い、自分の環境を整理しています。
――俳優として、やってみたい役はありますか?
暗〜〜〜〜い役ですかね(笑)そのほうが自分の本質には近いというか。もともと内向的で、本を読むか2ちゃんねらーしているかで、活発な方ではないのですが、いただける役は明るくて強気なタイプが多くて。今は社会人として仕事をする上で、特にプロデューサーの時はしっかりしなくちゃ、人と積極的にコミュニケーションをとらなきゃ、と「なりたい自分」を務めている感覚で。でも元来は自分に自信がなくて、いろいろなことを気にしてしまう、ただの気弱な人間なので…。その根っこの部分に寄り添ってあげられるような役が出来たら、一緒に心中出来そうだなって。
「映画をやりたい。そのために何でもやってきた」からこそ、のキャリア
――俳優として映画や舞台、テレビドラマなど幅広く出演しながら、プロデューサー、ドローンパイロットにも取り組んでおられます。なぜ多彩なキャリアになっているのでしょうか。
自分でもこうなるとは思ってなかったんです。好きな事と求められる事をやってきたら、こうなっちゃって、自分が1番びっくりしてます。俳優としては、もともと映画に参加したい気持ちが大きかったのですが、商業作品にはほとんどご縁がなくて。SNSでショートコンテンツを作ってみたことをきっかけに、ショートドラマやテレビドラマに参加できるようになると、こちらの方が求められたんですよね。私は映画には愛されていないのかな…と落ち込んだ時期もあったのですが、映画でもドラマでも、その役を誰よりも愛して、お芝居相手の方と向き合って、という普段大切にしているところは、別に映画でもショートドラマでも変わらないな、と自分の中で気づいてからは、もうどんな作品でも向き合える役があるならやりたいです!というスタンスです。

――プロデューサーについては、どのようなきっかけでしたか。
子どもの頃、「なんでなんで星人」だったんです。物心ついた時から、いろいろなことに疑問を持っちゃって、その中での一番大きな問いが「なんで生きてるんだろう?」でした。この答えが見つからなかったら、いつか生きるのが嫌になって死んでしまうんじゃないかと思っていて、死なないために生きる意味を知りたかった。
それで周りを見渡したら、大人たちは毎日仕事している、生きていくためには仕事が必要。それならせめて、心の底から好きだと思える、一生頑張れる、死ぬ気で頑張れるような仕事に就きたいと思って。
試行錯誤した結果、エンタメの世界は飽きないなと思って、家で一人でできることとして、最初は脚本を書いてみたんです。書くことは孤独な辛さ以上に楽しかったですが、もっと大きく物語を創り上げるということをやってみたいという気持ちが出てきました。そこから制作の勉強も始めて、やっていくうちに、プロデューサーとして最初から最後まで作品づくりに関わりたいと思うようになりました。
――俳優とプロデューサーと、厳密にはどちらが先だったのですか?
完全に制作が先ですね。その時は、まさか自分が表に立つなんて思っていなかったです。「現場を学ぶためにはどうすればよいでしょうか」と、ある脚本家の方に相談してみたら、今なら小劇場の舞台を紹介できるから、作品づくりには芝居も大切だし、舞台に立ちながら学ぶのが近道なんじゃないか?とアドバイスを受けたんです。で、私は単純脳なので「わっかりました!!!」と小劇場の舞台に入ってみたのが、俳優としては始まりですね。
――小劇場の舞台に出演するということは、出演だけじゃなくて周りのことを全部やらなくてはいけない。
小道具の準備や舞台の設営は一緒にさせていただきました。それ以外は俳優部として入りながら、各部署の皆さんに質問したり、動きを見たりして、勝手に学ばせていただいてました。実は高校生のときに芸能事務所にスカウトされているんですが、その時は「自分が表に立つなんてありえない」と思っていて、人の前で話すだけでも苦手なのに、芝居なんて出来ないし、自分に自信もないし、絶対に無理だと思っていました。小劇場では制作の勉強をするという明確な目的があったから、躊躇なく飛び込めましたね。それで無理だと決めつけていたお芝居に出会えたのは、ある意味ラッキーな収穫でした。
――プロデューサーの楽しみ、魅力ってどんなところにありますか。
全ての分野に関われるのはやっぱりプロデューサーだけなので、企画立ち上げからの過程と、それが世の中に生み出される瞬間は、毎回楽しいです。ゼロから思い描いたものをつくり上げて、それを見て何かを感じてもらうということは、子育てに近いのかもしれないと思ったりもします。自分の愛する子どもがいて、自分がいいと思ってそういう育て方をするわけじゃないですか。でも各所で意思が出てくるから、自分の思う通りにはいかないこともあるし、意見を尊重してあげないといけない時もある。そんな日々の向き合いを経て、これが私の子どもです、と見てもらったときに、自分の子どもを褒められると、やっぱりみんな嬉しいと思うんですよ。作品づくりは、そういう感覚に近いかもしれないです。私には、子供いないですが(笑)
――ドローンパイロットについては、どのようなきっかけでしたか。
私は誰かに師事したり芸術学校を卒業したりしていなくて、前述のように全て現場で学ばせていただいたのですが、とある撮影で助手として参加した時に「ちょっと裏でドローン飛ばしてきてよ」と言われたのがきっかけですね。それでドローンを飛ばしてみたら、もう楽しくて楽しくてしょうがなくて。それまで無趣味だったので、人生で初めてできた趣味がドローンだったんです。そこからまさか仕事になるとは思っていなかったのですが、『日本ボロ宿紀行』にキャストで出演が決まったときに「実はドローンを入れたいと思っていたから、最終回飛ばしてみてくれないか?」という、そんなきっかけだったかと思います。
――藤井道人監督から言われたのが、ドローンパイロットのきっかけだったのですね!
そうなんです。ドローンを先駆けて駆使されていた監督さんだったかと思います。今もドローンを作品でよく使われる方なのですが、当時ドラマでもドローンの画を使っている方はあまりいなかった中で、すごくドローンの画作りも活かし方も上手だったので、私もそのおかげもあって作品を見た人から依頼が入るようになりました。あ、でも確か最終回の監督さんはアベラヒデノブさんです。アベラさんも才能溢れるとっても素敵な監督さんなのですが、エンドロールが載る最終カットに使っていただいて。ドローンは趣味として始めたので自分で営業したことはないのですが、ありがたいことに作品から作品へと声をかけてもらって、今の状況になっています。
GeneTheaterアンバサダーはぜひやりたいと思えた
――GeneTheaterアンバサダーについては、引き受けてくださって本当に感激しています。
こちらこそです!

――GeneTheaterアンバサダーを引き受けていただいた理由を、改めて教えていただけますか。
インディーズ作品やクリエイターの支援を理念として掲げていることが一番の理由です。また、短編作品というのが、私が星新一のショートショートシリーズが好きで、物語を好きになるきっかけでもあったので。あとは、アンバサダーなんて恐れ多いといつもなら考えてしまうのですが、GeneTheaterに関してはなぜか珍しく「私がやることで、いい効果、いい波を何かしら生み出せる気がする」と思えたのです。自分がやってきたこと、GeneTheaterさんの考えが全くと言っていいほど同じだったので、そんなことあるんだ!みたいな。
――そうなんですね。嬉しいです。
お話いただいたときは嬉しさの反面、私でいいんだろうかという迷いもよぎりはしたのですが、直接お会いしてお話を聞かせてもらって、是非やらせていただきたいなと思いました。
――身に余る光栄ですね。
こちらこそです。井村さんもすごいキャリアですよね。
――私は普通の企業勤めだったので、全然特別ではないと思うのですが。
安定した企業勤めから転身し、新しく挑戦するのはなかなかできないことだと思うんです。ご一緒に、何かお力になれたら、とおこがましいですけれど思いまして、GeneTheaterも素敵な企画だなと本当に思いました。
――感激です。ここでインタビューを終わりたいぐらいです(笑)。MIRRORLIAR FILMSに関わっておられますが、短編映画の魅力をちょっと教えていただけないでしょうか?
そのままですが、短時間で一つの作品を観ることができる点ですね。また、説明過多にならないので想像を膨らませられる余地があるのも、短編映画の楽しみ方のひとつかなと思います。クリエイターの皆さんが挑戦しやすい点も魅力ですよね。
俳優もプロデューサーも続けていきたい覚悟を決めた
――俳優をやっていこうと決意したのはいつ頃だったのでしょうか。
覚悟を決めたのが、28歳頃でしたね。
――遅めですよね。
めちゃめちゃ遅いです。覚悟決めたのはそこかもしれない。やめようと思っていたんです。
――それは制作をやっているから?
プロデューサーとしてやはり時間が足りないというのが一番でしたし、体力的にも2つの役割なら体が2つ欲しいくらいで。私の場合はさらにドローンもあって、何でもかんでもは無理かなと思って。今は増えてきましたけど、当時は俳優部と制作を兼任している人も少なかったので、「お前みたいな中途半端なやつは何も出来るわけがない」とか、仲の良かった業界の方に突き放さることも多かったかったので、3年ぐらい、毎日「1つに絞らなきゃ。やめなくちゃ」と思い続けていて。でも結局、やめられなかったんですよね。そうして毎日悩んでいた時に、ふと「3年悩んで決められないなら、もういいか」と思って。「自分はこういう運命だったんだ、やれるところまではやってみよう。中途半端だと言われないように、どちらも頑張ればいいんだ」と覚悟が決まったのが、28歳頃でした。当時は、メインPとラインP作品を3本と、自主企画の宣伝配給とかもあったので、裏方として1番抱えていた時期だったんじゃないかな。朝10時から朝4時まで毎日働いて気絶寝してみたいな、人の生活してないぐらいになって。どれか一本にしぼろうよ、と体が悲鳴をあげても、心が辞めたくないと言ったんですよね。たぶん、そんな時でもやりたいって思いが消えなかったので、逆に覚悟が決まったんだと思います。

――幼少の頃は奄美大島に住んでいたとのことですが、映画館はありましたか。
ありました。でも、新作がすぐ来ないんですよ。1カ月遅れとかでしたね。映画館は時々行っていました。テレビで金曜ロードショーを観ることも多かったですけど、子どもの頃は映画というより本が好きでした。小学1年生から6年生まで、図書カードに記録した貸出冊数が、学内でずっと1位みたいな子どもでした。1日の最大冊数を毎日借りて、読んでいましたね。
――その後東京に来られて、生活のギャップはありましたか。
そうですね、電車に初めて乗って、人の数も本当に多かったですが、そういうのに、あまり反応できないタイプだったんですよ。海外に行ってもすぐ現地に順応しちゃうし、そこでトラブルが起きたとしても、すぐに受け止めちゃって、動じない。そんな感じなので、当たり前にホームシックもゼロでしたし、俳優をやるまでは、心がないんじゃないかってぐらい、さまざまなことをすんなり受け入れてしまうような癖がありました。怒りとか悲しみとか、驚きとかがあまりなかったです。今思えば何処か麻痺していたというか、傷つかないようにそうしている自分もいたのかなとは思います。俳優になってからいろいろな感覚や感情を、自分の中に取り入れていったという感じで。それもあって、俳優を辞めたくなかったのかもしれないです。自分を人間らしくさせてくれたというか、本当の意味で、生きるということを教えてくれた感じがあったので。
――演技はどこかで学ぶ機会があったのでしょうか。
ほぼ独学ですね。メソッドなどを学べるところに行ったこともあるのですが、教えられれば教えられるほど、駄目になっていってしまうタイプだったんです。その先生のやり方が全てだと、思い込んでしまうので。
本来は、教わったことを自分の中で咀嚼してから試してみるというやり方が一番いい学び方な気がするのですが、私は元々の自己肯定感の低さもあいまって、人に言われたことが全部そのまましみ込んじゃうから、少しでもそれで自分の中に引っかかりができるとイップスみたいになって駄目になってしまう、というのを何回か経験して、どこか一つのところで学ぶのは危険だからやめよう、と思いました。
――なるほどそれは危険ですね。
そうなんです。長い時は半年くらいイップスになってしまって何も出来なくなっちゃって。そこからは、自分でその時々に必要なものを研究して、なるべく自己完結で吸収できるようにしています。
下京慶子の現在地。世界に通用する作品をつくる
――2025年3月現在、これから目指していきたいことがあれば教えてください。
今日現在でいいんですよね。
――来年になったら変わっても別に構わないです。
わかりました。端的に言うと、世界で戦える、世界の映画祭で賞が取れるような作品をつくりたい、というのが今一番の目標ですね。
――プロデュースでしょうか。
そうですね、まずはプロデュースの方で。
自分が出たい気持ちとつくりたい気持ちが一緒になってしまうと、本当につくリたいものを見失ってしまう気がするので、そこは切り離して考えたいと思っています。
これまでの制作経験を経て、今の自分が「何が何でもつくりたい」と思える作品づくりに挑戦したいです。
これまでは有難いことに求めていただいて参加する作品が多かったので、次は自分発信で作品づくりをしていきたい。
沢山の尊敬する監督、キャスト、スタッフの皆さんと出会い、作品を作ってきたおかげで、自分が本当にやりたいことは何だろうと見つめ直すことができ、「死ぬまでに1作品でいいから、自分が死んだ後も人の心に残る作品をつくりたい」ということが、実は最初の目標だったというのを、最近思い出しまして。「あれ、もう時間がない!じゃあそれやろう!」というのが、今の私です。
井村哲郎
以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。
自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。

