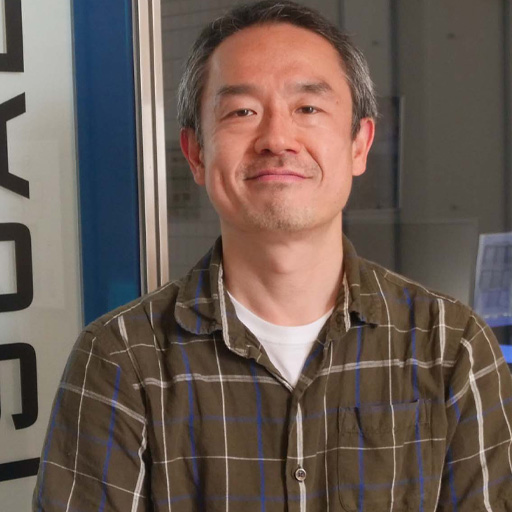応募条件が制作を始めて長編作品が3本以下の監督
──「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」はどのような経緯で設立されたのでしょうか?
SKIPシティは2003年にオープンして、スタジオや編集室、映像ホールなどが揃っています。その頃はちょうど映像制作にデジタル化の波が進んでいて、デジタルカメラで撮影することで撮影コストが下がったり、編集方法が変わったりして業界的にも過渡期にありました。安価かつ手軽に映画が作れる時代がやってくるということで、SKIPシティとしても若手クリエイターを応援したいと映画祭がスタートしました。
映画祭を開催することで埋もれがちな若手映画監督を発掘し、受賞者にSKIPシティの施設を利用してもらうことで制作のバックアップをする。映画祭はそうした2つの役割を持っています。
──「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」のコンセプトは何ですか?
「若手映画監督の発掘」です。
制作を始めて長編作品が3本以下の作品であることが応募条件になるんですが、それでも上質な映画がたくさん集まっています。「こんなに素敵な若手の映画があるよ」とどんどん示していきたいです。
応募は国内だけでなく、国外からも広く募っているので、来場して作品を観ていただくだけで「いま世界でどんな映像制作が行われているのか?」がわかります。新鮮で鋭い感性の作品をたくさん鑑賞できるということで、本映画祭のお客さんはとても目が肥えているんですね。
── たしかに、SKIPシティ映画祭目指す若手監督は多いと感じます。
クリエイターのみなさんにそう思ってもらえるのは本当にうれしいことで、これまで20年積み上げただけのことはあるのかなと感じます。
過去の受賞監督さんが活躍されているのもありがたいことです。本映画祭は産業的に成功しそうな方をピックアップしているわけではないので、純粋なクリエイティブの才能が優れた方が映画業界でしっかり活躍されていくのを見ると、若い後進の希望になっていると思います。
SKIPシティ映画祭でグランプリを取った監督が、翌年カンヌ映画祭で監督賞を受賞
── 過去の受賞者にはカンヌ映画祭で賞を取った監督もいますね
2007年のSKIPシティ映画祭で『うつろいの季節(とき)』で最優秀作品賞を取ったヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督は、翌年の2008年にカンヌ映画祭監督賞を受賞しています。2007年度のSKIPシティ映画祭のグランプリの賞金が1000万円だったこともあり、本映画祭の賞金はカンヌ受賞作品の制作に使われたともいわれています。
ジェイラン監督はその後、パルム・ドール賞も受賞して、今や映画をつくれば世界的な映画祭のコンペに入るという有名監督になりましたね。そういう方が参加してくれたことは事務局としても大きな励みになっています。
── 受賞作品には海外の作品が多いですが、国内より海外からの応募が多いのでしょうか? 国内外でクオリティのレベルに違いはありますか?
海外だと駆け出しの新人監督にもプロデューサーがついて予算がもらえるという国があるんですね。国から助成金が出るとか。金銭面でのバックアップがあると、新人監督でも素晴らしい映画を撮れる環境が整うんです。
一方で、日本の若手は自分の持ち出しで自主制作で長編映画をつくることが多いので、長編映画3作品目までに制作された作品は、なかなかクオリティを高めることは難しいようです。受賞のための選考は国内・国外問わず公平に行っていますが、そもそもの制作費の部分で差がついている印象はあります。
── 海外の若手クリエイターの制作事情について詳しく教えてください
ヨーロッパでは、初監督作品でも自国のみならず、いろんな国からお金を集めるというのが可能なんです。それを実行するのはプロデューサーなんですが、プロデューサーの役割や動き方が日本と海外でだいぶ違います。
海外は「プロデューサーはお金を集める人」という感覚ですが、日本映画は製作委員会方式をとることが多く、プロデューサーというと企画の進行管理やマーケティングを考える人が多いのではないかと思います。
たとえばフランスの場合、長編作品を初めてつくる、あるいは2本目を制作するという監督のための助成金があります。そういう枠が設けられているんですね。だから、プロデューサーも動きやすいし、新人監督とばかり組んでいる人もいます。すでに何本も制作している監督ですと助成金が下りにくくなって、ゼロから自力でお金を集めなければいけないので、プロデューサーとしても仕事がしやすいのかもしれません。
SKIPシティアワードの副賞が“映像制作施設の無償利用”
── 日本のインディーズ映画業界についてどう思いますか? また、インディーズ映画業界が良くなるために、何か必要だと感じますか?
お金がないカツカツの状態で制作する、というのが当たり前になっていますが、そういったインディーズ映画ならではの苦しみから抜け出すきっかけがあればと思います。
たとえば、ヨーロッパのやり方をならって国や自治体に助成金を出してもらうとか。それも、ちゃんと目利きのできるプロが認めた企画に十分なお金を出す、という。若手を育てることにもっと意識が向けば業界の流れが変わるかもしれません。
── 日本人では2009年に白石和彌監督が長編部門(現在の国際コンペティションに当たる)でSKIPシティアワードを受賞しています。2013年には『凶悪』を撮ったので、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭をきっかけにプロのキャリアをスタートさせたといえますね
白石監督は『ロストパラダイス・イン・トーキョー』で2009年に受賞したんですが、SKIPシティアワードの副賞が“映像制作施設の無償利用”でした。一定期間、プロ仕様の施設を自由に使えたので、『凶悪』では仕上げ作業の一部をSKIPシティで行ってくれました。
── 第20回で審査員を務める中野量太監督は、2012年にSKIPシティアワードを受賞しています。当時はどんな印象でしたか?
当時はまだまだ知られていない存在でテレビのお仕事をされていました。本映画祭に応募されたのも、いわゆる自主制作作品でしたね。
だから、SKIPシティ映画祭で認められた後、ほどなくして『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞にノミネートされたというのは、やっぱり優れた才能をお持ちなんだと思います。
本映画祭受賞作品は様々なフォローアップも
── コンペ部門には、海外からは長編のみ応募できる国際コンペティションがあり、日本作品に対しては長編と短編部門を持つ国内コンペティションがあります。日本人は国際コンペに応募できないのでしょうか?
日本人は国内コンペ・国際コンペどちらにも応募できます。
たとえば、今年は串田壮史監督の『マイマザーズアイズ』が国際コンペに選ばれていますが、この作品はクオリティが非常に高く、国際コンペでも十分に競える映画と事務局が判断しました。つまり、日本の長編作品の応募は一括で行い、事務局で国際コンペ、国内コンペに振り分けています。
── 受賞作品にはどんなフォローアップがありますか?
本映画祭の受賞作品を海外の映画祭に紹介するというアプローチをしています。海外のプログラマーの方々に見ていただいて、海外でも評価されるよう推薦します。
去年の例でいうと、国内長編部門に選ばれた余園園監督の『ダブル・ライフ』が、7月に本映画祭で上映して、11月に国際映画製作者連盟(FIAPF)が認定するタリン・ブラックナイト映画祭のファーストフィーチャーコンペティションに出品されました。
カンヌやベルリンと並ぶクラスの映画祭のデビュー作品コンペに出たんですね。
ドイツで開催されるニッポン・コネクション(優れた日本映画を発掘する映画祭)のプログラマーには毎年出品作品をすべて見てもらっています。先方からは、長編・短編どちらも観たいと言われているんですね。
── 映画館での上映はしているのでしょうか?
各方面に作品のご紹介は積極的にしているのですが、公開となると難しいところがあります。過去には、本映画祭で選ばれた作品を劇場公開する“Dシネマプロジェクト”や、“最速・最短全国劇場公開プロジェクト”という試みをしたことがあります。
現状は配給のお手伝いが確実にできるとは限らないため、「絶対に劇場公開する」とは言えないのですが、事務局としてももっと手厚くやりたいところではあります。
制作する部分では、受賞者に施設の貸し出しをしたり、過去の受賞監督さんに映画祭のオープニング作品を作っていただいたりとフォローアップできている実感があるので、今度は「観せる」という部分でもお手伝いできればと思います。
── 第20回の応募状況を聞かせてください
第20回の応募数は過去最高の1,246本でした。日本の長編作品は例年だと70本くらいなんですが、今年はそれをかなり上回る92本の応募がありました。短編は205本で、日本作品はトータル297本です。
コロナ禍が明けたとはいえ、まだまだ影響があると思うのですが、これだけの作品が集まったというのは正直驚きでした。そして、ありがたく感じました。
── 第20回のスケジュールを教えてください
2023年7月15日から23日まで、埼玉県川口市のSKIPシティで開催されます。オンライン上映は7月22日から26日の23時までです。
授賞式は最終日の7月23日、SKIPシティの映像ホールで行います。
ここ数年はコロナの影響で国内のお客様はもちろん、海外のゲストに来場いただけなかったんですが、今年はたくさん来ていただけるとお返事をもらっていますし、我々も盛り上げていきたいと思っています。
── 第20回の見どころを教えてください
コンペ作品は応募数も多く、厳選に厳選を重ねて素晴らしい作品を選びました。
コンペティション部門の24作品は、どれをとっても「面白いです!」と自信を持っていえます。残念ながら選に漏れた作品も、今年に限っては「泣く泣く落とさせていただいた」という状況で、ご紹介したい作品がほかにもたくさんありました。
国内作品はいつになくバラエティに富んで、それは技術が高いとかお金をかけているという意味ではなく、アイデアと表現力に優れた質の高い作品がいくつもありました。
──「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」を今後どのように発展させていきたいですか?
作品の配給まで整えられるお手伝いができれば、と常に思っています。
制作のフォローアップはある程度できているんですが、映画はたくさんの人に見て楽しんでもらうものですから、そのサポートがより手厚くできればいいなと考えています。
また、20年という年月を重ねるなかで、国内外で高い評価を得る監督さんが何人も現れるようになりました。応募作品のクオリティは年々上がっていますので、上質な作品を取りこぼさず多くの方々にご紹介し続けていくのは、この映画祭の使命と感じています。
井村哲郎
以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。
自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。