インディーズ映画『さめざめと、』でセリフが印象に残る理由
── 板野監督のデビュー作の「さめざめと、」から伺います。まずタイトルの『さめざめと、』があまり一般的な言葉ではないと思うのですが、この言葉をタイトルに選んだ理由を教えてください。
もともとは『寝ても覚めても』というタイトルにしようとしたのです。しかしすでに同じタイトルの映画があったので、他のタイトルを考えました。「さめざめと」とは“涙を流して泣き続ける”という意味です。映画も粛々と考えている日常の中で、悲しみが静かに続くことを描いているので『さめざめと、』にしました。
それと「さめざめ」の中に「目覚め」だとか「覚める」とか人がなくなった後の温度感をタイトルに込めたかったこともあります。そして『さめざめと、』の「、」で、人がなくなっても日常は続いていくということを表現しています。

──「勝手に死んでんじゃねーよ」とか「べらぼうに人間へたっぴ」などセリフが印象的でした。
『さめざめと、』が初めての監督作品なのですが、それまでも文章を書くのがとても好きでした。
中学生のときから、その時に感じた感情をノートに書いていて、そのノートを参考にしました。そのノートには、その時の自分の気持ちをストレートに書いていたので印象深く受け止められたのかもしれませんね。
──主人公のゆかりがおじいちゃんのことを本当に好きだったことがわかります。特におじいちゃんへの愛情を描いてるのはどのシーンですか?
野菜をいつも送ってくれていたシーンでしょうかね。直接会って言われるやさしさではなくて、言葉はないけれども遠くから見守っているみたいなところに、本当の人のやさしさがあると思うんです、だから主人公のゆかりが時間をかけて料理をするシーンはおじいちゃんへの感謝のシーンを表していて、とても重要なシーンなんです。
── カメラワークが主人公の気持ちをうまく表現していますね。カメラマンとはコミュニケーションをかなりとられたのですか?
自分がこういうふうに撮りたいということはカメラマンと綿密に相談しました。初監督作品であり、自分も主演しているので、かなりこだわりました。
短編映画紹介

『さめざめと、』(ジーンシアターで配信) 視聴はこちらから
ストーリー
「あのね、実はね、死んじゃったんよ……おじいちゃん。」主人公のゆかりの元へ舞い込んだ、突然の訃報。優しかった祖父が亡くなったという、母からの知らせだった。世間では新型コロナウイルスが猛威を振るっていることを受け、家族は“オンラインお葬式”で祖父を見送ることとなった。バラバラだと感じていた家族が画面の中へ一同に押し込められ、そして死者を見送る。コロナ禍であろうと変わらない、複雑に交差する人間の気持ちの核心に触れた、考えさせられる作品。
劇場公開される『魚の目』のキャラクター設定について
── 続いて映画館でも上映される『魚の目』について伺います。板野さんは監督に加えて脚本も書かれていますね。主人公の2人はもちろん、脇を固める登場人物一人一人のキャラクターが強いなと感じました。登場人物の設定にはこだわったのですか?
脚本を書いている段階で、この人物はこういうキャラクターにしたいと言うのがありました。そして役者さんをオーディションで決め、そこから役者さんに自分の考えた登場人物のキャラクターを伝え、役者さんと「この登場人物はこういう時はこういうことをやってそうだよね」とか話し合って、一緒につくり上げた感じです。実際に役に魂を吹き込むのは役者さんなので、役者さんとはかなりコミュニケーションは取りました。
── 特に力を入れた登場人物はいますか?
全ての登場人物に力を入れました。特にと言われると答えづらいのですが、あえて聞かれれば、漢文の先生ですね。彼は物語のキーになる人でもあるし、自分が高校生の時に実際に救われた言葉などを反映しました。
映画『魚の目』のワンシーン

ストーリー
“魚の目に水見えず、人の目に空見えず”
そこにあるがゆえに、目の前のものは見えない。
優等生の殻をかぶり自分の本心を出せない怜奈。
先生と逢瀬を重ねる自由奔放な海。
振り向かない幼馴染にシャッターを向け続ける楽人。
密やかに愛する人の幸せを願う理。
焦げつく恋の視線をぶつけるあかり。
弱さを抱え、狭い水槽の中でもがき生きる彼女たちの青春群像劇。
-私たちはまだ、弱さを上手く愛せないでいる。
劇場公開される『魚の目』のテーマは“人の弱さ”
── 登場人物全員が心に痛みを抱えている人たちだなと思いました。ただ映画を観た時になぜか暗い感じがしませんでした。演出面でこだわったことはありますか?
テーマ自体が「人の弱さ」を扱っている作品なので、「暗い感じになりかねないな」ということはずっと思っていました。だけど、自分では暗い感じの映画にしたくなかった。自分自身が自分を愛して、その弱さを認めてあげることで、生きやすくなるんだよということを言いたかったのです。このことは決して後ろ向きではなく、前向きな考えだと思うのです。なので、最後は希望を持てるような脚本にして、映像面でも疾走感を出してみました。
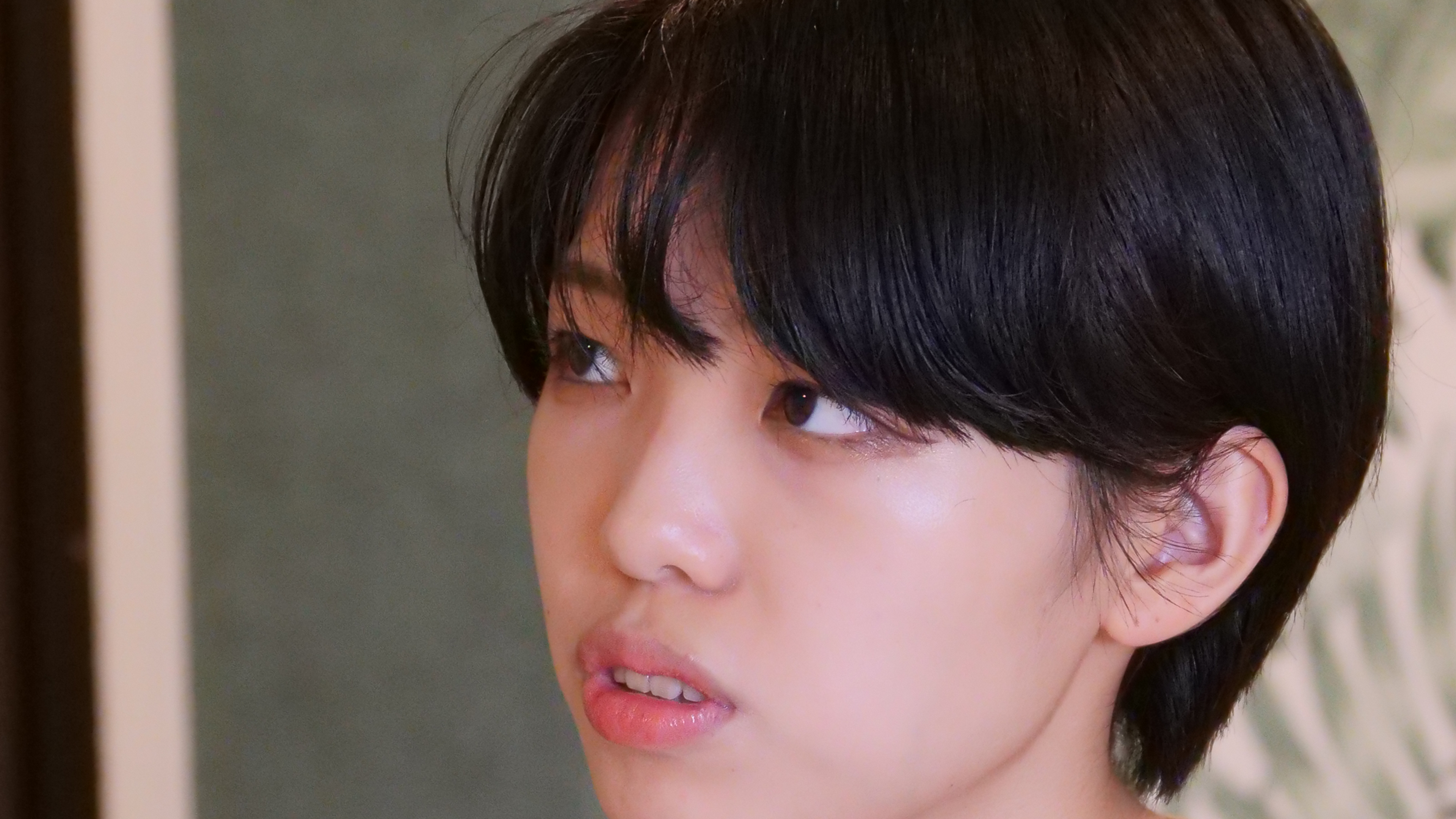
── 人の弱さがテーマなんですね。
そうです。キャッチコピーも「私たちはまだ、弱さをうまく愛せないでいる。」にしました。作品の中でも漢文の授業シーンで出てくる「山月記」を取り上げています。実はキャッチコピーは私が高校生の時に「山月記」の感想文に書いた言葉なんです。「山月記」というのは自分の弱さをプライドのために認められなくて虎になってしまうという話なんですが、『魚の目』では認められなくて虎になるのではなく、自分の弱さを認めて、誰かのために人のために、その弱さを愛せたらいいよね、という想いを込めてつくりました。弱さを認めることが重要なのだと思っています。
──『魚の目』というタイトルをつけた理由を教えてください
『魚の目』というタイトルをつけた理由は2つあります。
1つは「魚の目に水見えず人の目に空見えず」ということわざから取りました。これは“魚の目に水が見えていなかったり、人の目に空気が見えていなかったりするように大切なものは自分では気づきにくい”という意味なんです。自分自身や相手のことを気づくのは難しいっていうことなんです。
2つ目は私が高校生の時に、学校の先生に「板野さん、死んだ魚の目見たいな目してるで」って言われたことがあったんです。その時は「なんて酷いことを言うんだ」とすごく頭にきたんですね(笑)。今になってみると高校生の時に自分が見えていた世界や見えていなかった自分自身について考えると、今回の映画のテーマに合っているなと思い、タイトルをつけました。
あの時の先生に見て欲しいと思っています(笑)。

数々の映画祭で受賞したことについて
──『魚の目』は第15回田辺弁慶映画祭 キネマイスター賞、第10回関西学生映画祭 観客賞、第24回京都国際学生映画祭 行定勲賞など数多くの映画祭で受賞していますね。
映画祭での受賞は嬉しかったですね。自分がつくった作品が受賞した喜びもあったのですが、作品づくり関わってくれた多くの人に恩返しのような気持ちもありました。映画はもちろん一人ではつくれないので、『魚の目』に関わってくれた人、全員に対して成果が出たということで、ホッとした気持ちもありました。
──『魚の目』は、映画館でも上映されますね。
そうなんです。2022年9月22-24日にテアトル新宿で、『魚の目』と私の最新の監督作『煙とウララ』が上映されることになりました。さらに2023年10月には大阪梅田のシネリーブルでも上映されることが決まりました。私も行きますので、是非、観にきてもらいたいですね。(※現在、上映は終了しました)
好きな映画監督はグザビエ・ドラン監督
── 好きな映画監督や映画があれば教えてください
グザビエ・ドラン監督が好きです。特に「Mommy マミー」が好きです。日本では是枝裕和監督が好きです。“家族”とか“愛”をテーマにした作品や監督が好きです。“家族”とか“愛”とかいうと、いまさら感はありますが、やっぱり、そこがとても重要なんですね。

── キャリアについて伺います。現在、大学生ですね。映像はいつから作られたのですか?
大学生2年の春に初めて映画をつくりました。ジーンシアターでも掲載している『さめざめと、』が初めての作品です。写真を撮ることと文章を書くことは以前から好きでしたが、映画をつくりたくて大学に入ったわけではないのです。大学で「映像制作ワークショップ」という授業の中で初めて映像制作をしました。
授業では3分くらいのレターメッセージ動画をつくるという課題だったのですが、私がその課題を読んでなくて、めちゃくちゃ長い脚本を書いて送ったら、担当の武村敏弘先生が、なぜか「これをもとに短編映画をつくろう」ということをいわれ、びっくりしました。そして脚本、監督に加えて主演まで自分がやることになって『さめざめと、』をつくることになったのです。『さめざめと、』は、実は私が全然授業を聞いてないことがきっかけとなったのです(笑)。
── これからどんなキャリアを積んでいきたいと思われていますか?
脚本を書くことはこだわっていきたいと思っています。その延長線上に監督があると思っています。映画だけでなく、ドラマなどにも興味があります。
井村哲郎
以前編集長をしていた東急沿線のフリーマガジン「SALUS」(毎月25万部発行)で、三谷幸喜、大林宣彦、堤幸彦など30名を超える映画監督に単独インタビュー。その他、テレビ番組案内誌やビデオ作品などでも俳優や文化人、経営者、一般人などを合わせると数百人にインタビューを行う。
自身も映像プロデューサー、ディレクターであることから視聴者目線に加えて制作者としての視点と切り口での質問を得意とする。

